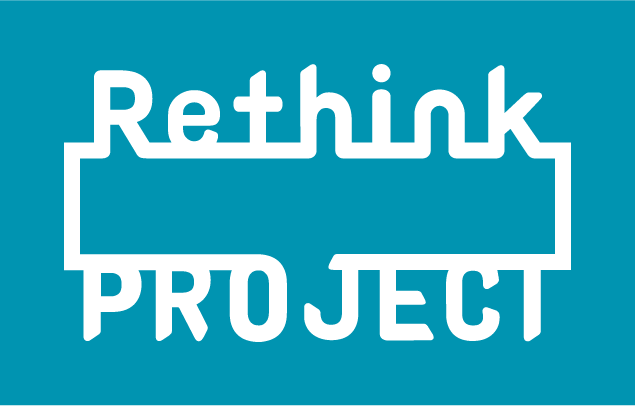「笑いの正しい使い方」を教えて、日本中の学校からいじめをなくしたい〜お笑い芸人/オシエルズ 矢島ノブ雄さん・野村真之介さん〜
2020年8月13日

(前回からの続き)
暗黒時代を救った東大との仕事
―――お二人はコンビ結成当初より、芸人と教師の両立を考えてこられたようですが、進む道に迷いなどはなかったのですか?
野村:実は僕たち、アイデンティティを失っていた暗黒時代がありました。芸人も教師もだと、“どっちつかず”に見えてしまうんですね。だから、芸人からは「学校の先生もやってるってどういうこと? 芸人なら芸人として舞台に立てよ!」って言われていたんです。一方で、教育関係の人からは「ふざけてるの?」と言われてしまう。結果的に、どちらの業界でも力を発揮できないという時期がずっと続いていました。

―――今はもう、そのジレンマから抜け出せたんですか?
矢島:おかげさまで、今は自分たちの道が見えてきました。
人生の大きなターニングポイントがあったとすれば、2015年に東京大学の方と仕事をしたときです。「企業研修でもお笑いの力が必要」と声をかけてくださった方がいて、そこからとんとん拍子に東大の大学院の方とつながった。
その後、東大が河合塾のマナビスにアクティブラーニングのプログラムを提供することになったとき、「マナビラボ」という教育者向けサイトのコンテンツのひとつを僕らに任せてくれたんです。そこから、教育関係のお笑い芸人という立ち位置が定まったと思っています。

メジャーでは売れない。30万人の子どもに見てもらえればそれでいい
―――テレビに出たい、M1でいい成績を取りたいなど、お笑いの世界で勝負したいと思うことはありませんか?
野村:もちろん憧れはあります。でも、お笑いはとても厳しい世界。本気でお笑い芸人になりたいなら、年に300回以上は舞台に立つくらい、ただひたすら芸を磨き続ける長い時間が必要なんです。
それなのに、M1は5000組が挑戦して、決勝に残って有名になるのはわずか2,3組。僕らはそこまでの時間を芸人になるためだけに費やせない。それもあって、僕らは“教育”という世界を捨てられないんです。
矢島:よく野村くんと話すんですけど、たぶん僕らはメジャーでは売れない。お笑いのメインストリームでは生きていけないと思うんです。メインストリームで生きるためには、実力も運も必要。食えない時代はバイトもしないといけない。でも、僕は結婚して子どももいるし、まず食べていかないといけないですよね。

だけど、日本の教員のうち1万人が僕らを知ってくれれば、きっと食っていけると思っています。別に、1億何千万人の日本国民全員に知ってもらう必要はないんです。1万人の教員のうち、1000人が僕らを学校に呼んでくれたとする。その各学校の全校生徒が300人としたら、結果的に僕らは30万人の子どもに芸を見てもらえる。30万人もいるなら、それでいいじゃんって。
「笑いの正しい使い方」を教えて、日本中の学校からいじめをなくしたい
―――オシエルズが「お笑い×教育」で目指しているものは何ですか?
矢島:オシエルズとしては、「日本中の学校からいじめがなくしたい」と本気で思っています。そのために、自分たちがやれることを続けていく。笑いの正しさ、怖さ、正しい使い方を伝えていきたいです。
―――“笑いの正しい使い方”ですか。
矢島:ワークショップをやっていると、子どもの対応に困っている先生に出会うことが多いんです。

笑いは、良い笑いだけではないですよね。攻撃的な笑いもあり、そこから始まる子ども同士のトラブルもあります。「教師として、子どもの笑いにどう対応すればいいのでしょう、どう切り返せばいいのでしょう」と聞かれることもありますね。

子どもたちってずるい部分がある。例えば、多忙で余裕がない先生をからかってイライラさせて、ブチ切れたらそれを見てまた笑う、みたいなところがありますよね。子ども同士でも良くない笑いってあると思っています。人を笑うのは楽しい面もあるけれど、“あざ笑う”とかえって人を傷つけもします。
自分自身もいじめられていた経験があるので、そういう笑いの良くない部分について、きちんと向き合ってもらえるような活動をしていきたいですね。
笑いの可能性は“伝える”だけじゃない。笑いを受け止める側の意識
―――笑いには良い側面と残酷な側面があることを伝えていきたいと?
矢島:そうです。現在、お笑いを教育に活かそうという試みが増えてはいるんですが、ほとんどが“伝えるための教育”だと感じています。「ネタを作って演じてみよう。そして人を笑わせてみよう」という、伝えることだけにお笑いを取り入れているんです。正直に言うと、それってすごく気持ち悪いとすら思います。
自分から声を上げて主張することが苦手な子どもにとっては、笑いは伝えることだけが“正解”とされると、お笑い自体が苦手になるし、「自分には向いていない」という結論しかない。お笑いって本来、“笑わせる人”と同時に“笑う人”、笑うお客さんがいなくちゃ成り立たない。それなら、“観客として笑う側”からのアプローチもありだと思うんです。笑いの感じ方の教育です。

Aくんはこれを見て笑った。でもBくんは笑えなかった。なぜ笑える人と笑えない人がいるのか。そういう受け止める側の教育こそ、いじめの解決につながる“笑いの正しい使い方”だと思うんですね。「笑いを積極的に取れるお調子者だけが良い」とするのではなく、笑いを受け止める側の意識も重要です。それはダイバーシティ(多様性)にもつながり、もっと言えば文化の理解にもつながっていきます。
そう考えると、お笑いはとても深い世界。僕らは、よりスケールの大きな“笑いの可能性”に目を向けていきたいと思っています。
取材・文/小澤 彩 編集/下田 和